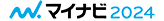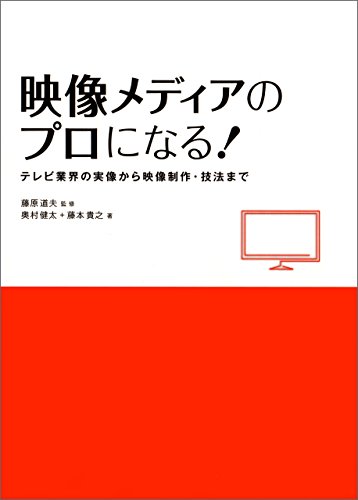『テレビには伝える事しかできないし、伝え続ける事が使命である』
あれから1年。
夏が来て、
秋が来て、
雪が降った。
そして冬が過ぎ、東北の地にも、まもなく春がやってくる。
この間、テレビをはじめとしたマスコミを巡る環境は一変した。
原発報道に端を発したマスコミ不信はかつてないほどに高まり、
ネット上にはあちらこちらに「隠蔽」「マスゴミ」といった言葉が踊る。
記者クラブ制度の弊害!と声高らかに叫ぶ者があれば、
テレビそのものを「くだらないもの」と一刀両断、
テレビを見ない宣言をする者、実に様々である。
お茶の間の中心でなくなって久しいテレビは既に娯楽の王様でもなく、
真実を伝える「箱」でもない。
しかし、そんな状況にありながらも、テレビディレクターである僕にとって、
この一年間はテレビの持つ力を再認識させられた一年間であったといえる。

テレビの力・・・、それは遠くに離れている人たちに対して、
一度に、同時に、そして大量の情報を瞬時に伝達できるということに他ならない。
単純計算すると視聴率1%で130万人。
世界で最高の発行部数を誇る読売新聞でさえ1000万部だというから、
テレビで視聴率10%を獲得すれば、読売のそれをゆうに凌ぐ計算となる。
あくまで理論上の数字でしかないが。
どこそこの避難所で食糧が足りないと放送されるや否や、
日本全国から食べきれないほどのおにぎりやパンが届く。
電話もメールも通じず、一切連絡が取れなかった親戚を
テレビ画面を通じて発見する。
もちろん、食糧が余りすぎた等、支援物資のミスマッチングを解消するために
ネット、特にソーシャルメディア(Twitterなど)と呼ばれるものが役立ったのも事実だ。
きめ細かな支援の妨げになる、という理由でテレビが批判されたこともあった。
しかし、あの時、僕たちにできたことは被災地の現状という「情報」を日本中に発信し、
被災地にフィードバックすることだった。
「瞬時」に「大量」の「情報」を「投下」することによって解決された問題も
非常に多かったように思う。
そう、「情報」は一時期、東北の人々にとって最大の「救援物資」だったとも言える。
しかし、そんなテレビの「画一的」な報道は、時に真実から人々の目を
反らすことに繋がったのもまた、一つの事実である。
岩手県の大槌町を訪れたときのことだ。
雨が降りしきる現場は、まだあちこちで煙が上がっていた。
車が燃え、家が燃えていた。刺激臭が鼻をつく。生きているものなど
そこには存在しないかのような光景・・・まさに地獄絵図が広がっていたのである。

自衛隊員が悲痛な面もちで、行方不明者の捜索にあたっていた姿は今でも忘れられない。
この岩手県でもっとも被害が大きかった街のひとつで僕は
テレビ報道のあり方について深く考えさせられることになった。
死者・行方不明者は1,282人にものぼり(3/2現在)、
特に町役場の職員は全139人のうち33人が死亡。
役場は津波の被害を受け大破し、復旧されることなく放棄された。
被害者の中には町長だった加藤広暉さんも含まれている。享年69だった。
僕がこの町に足を踏み入れたのは、復興の要となる町役場が機能不全に陥ったことによって
なかなか支援が進んでいなかった時。
住民の不安と疲れがピークに達していた頃だったと思う。
そんな現実がある一方で、加藤町長の死が「美談」としてマスコミで報じられ始めてもいた。
町民を守るために津波に襲われながらも最後まで役場に残って
町民の安全を優先させた、といった内容だったと記憶している。
確かにそうなんだろうと思う。
加藤町長の勇気ある行動によって助けられた命もあったはずだ。
しかし、僕はこの報道に若干の違和感を感じていた。
というのもマスコミ、特にテレビはこの手の話が大好きだ。
自己犠牲を省みずに行動し、命を失う。
貴き犠牲の上で生まれた新しい命・・・といった類のものだ。
誤解を恐れずに言えば、絵に描いたようなお涙頂戴モノを好むのが
テレビというメディアなのである。
さらには「視聴者のみなさんは、こういうお話が好みなんでしょ。」
などという、どうしようもなく上から目線で、
視聴率欲しさで番組を制作している輩がいるのも事実である。

町長の「美談」に目を奪われていて、見えなくなっている事実があるのではないか。
しかし一方で、職員の2割を超える人々が亡くなったというのも、また偽らざる現実だ。
震災が発生してから、役場が津波に飲み込まれるまでの30分間、
何が行われ、何が起きていたのかを取材して検証するのも、
我々の大事な役割なのではないか。
見方によっては地味な「ネタ」だけに、ボツになるかもしれない、
放送されることはないのかもしれない。それでも僕はカメラを回し続けた。
取材を続けていくと、加藤町長や役場の職員たちは、震災発生後、
役場の前に机などを出して災害対策本部を作ろうとしていたことが分かった。
老朽化した庁舎では危険だ、と判断したかららしい。
これまでに三陸を襲った津波被害の教訓では
「とにかく高いところへ逃げろ」とされていたにも関わらずだ。また防災マニュアルには
「庁舎が使用不可能になった場合は(高台にある)中央公民館に本部を置く」
と記されている。
「町長さんたち、何やってるんだろう。早く逃げればいいのに。」と
山の方へと避難しながら不思議がった町民もいた。
それなのに、なぜ?
取材によって浮かび上がった断片を繋ぎあわせてみると、おそらく真相はこうだ。
「加藤町長以下職員を含めて、防災マニュアルが徹底されていなかった。
津波に対する危機意識もあまりなかった。」
町の防災無線が「高台に避難して下さい」と呼びかける中、職員たちは
対策本部の会議を行うための机を並べていたのである。
結果、猛然と襲いかかる津波に気付いたときには、時既に遅しの状況であったことは想像に難くない。
次第に姿を大きくしていった「黒い固まり」は、
役場の屋上へと逃げようとする職員たちを次々と飲み込んでいったと、
目撃者は語っている。
もし加藤町長や役場の職員たちが防災マニュアルに従って
高台の中央公民館に対策本部を作ろうとしていたら?
もし先人の知恵が、彼らを高台へと導いていたら?
もっと危機感を持っていたら?
もしかして、亡くなった命の何割かが救われたかもしれないのだ。
起きてしまった自然災害は、もう元へは戻せない。
町が元の姿に戻ったとしても、失われた命はかえってこない。
時計の針を戻すことが誰にもできないように。
しかし、この悲しい教訓を取材し、放送することで、
また起きるかもしれない地震や津波の被害から救うことができる命があるかもしれない。
そしてそれができるのが僕たちの仕事でもある。
あの時、何が起きていたのか?
どうして命を落とすことになったのか?
耳障りのいい「美談」の裏にある事実に眼を背けることなく、
様々な角度から検証し報道していく。
そのための「トンボの眼」はディレクターにとって最も重要な能力だと痛感する。
たくさんの取材テープの中から、今、必要な情報、後世に語り継いでいくべき
貴重なひとかけらを探し出して放送し続けていくこと。
それがあの現場に立った僕たちテレビディレクターに課せられた使命なのだと、今は考えている。
すでに見放されたといっても過言ではないテレビが再び信頼を勝ち取るためには、
愚直に真実を見つめ、伝え続けていくしかないのだと思う。
去年8月に行われた町長選挙では元総務課長の碇川豊さんが当選し、
復興に向けて新たなスタートを切った大槌町。
どんな焼け野原からでも、人間はいつも立ち上がってきた。
必ずや大槌町も、再び、笑顔あふれる町に復興するに違いない。
人間の知恵と勇気がそれを可能にするのだということは、歴史が示すとおりである。
まもなく3月11日がやってくる。
いまテレビや新聞紙上では「あれから1年」といった言葉が踊っている。
しかし、それは単なる通過点に過ぎない。
東北の人々にとっては3月9日も、3月10日も、3月12日も、
そしてその翌日もそのまた翌日も、辛く苦しい日々が続くことも、また現実である。
テレビにできることは、あの日をいつまでも忘れないように
報道し続けていくことに尽きると信じている。
文責:メディアアーツ事業部 奥村健太